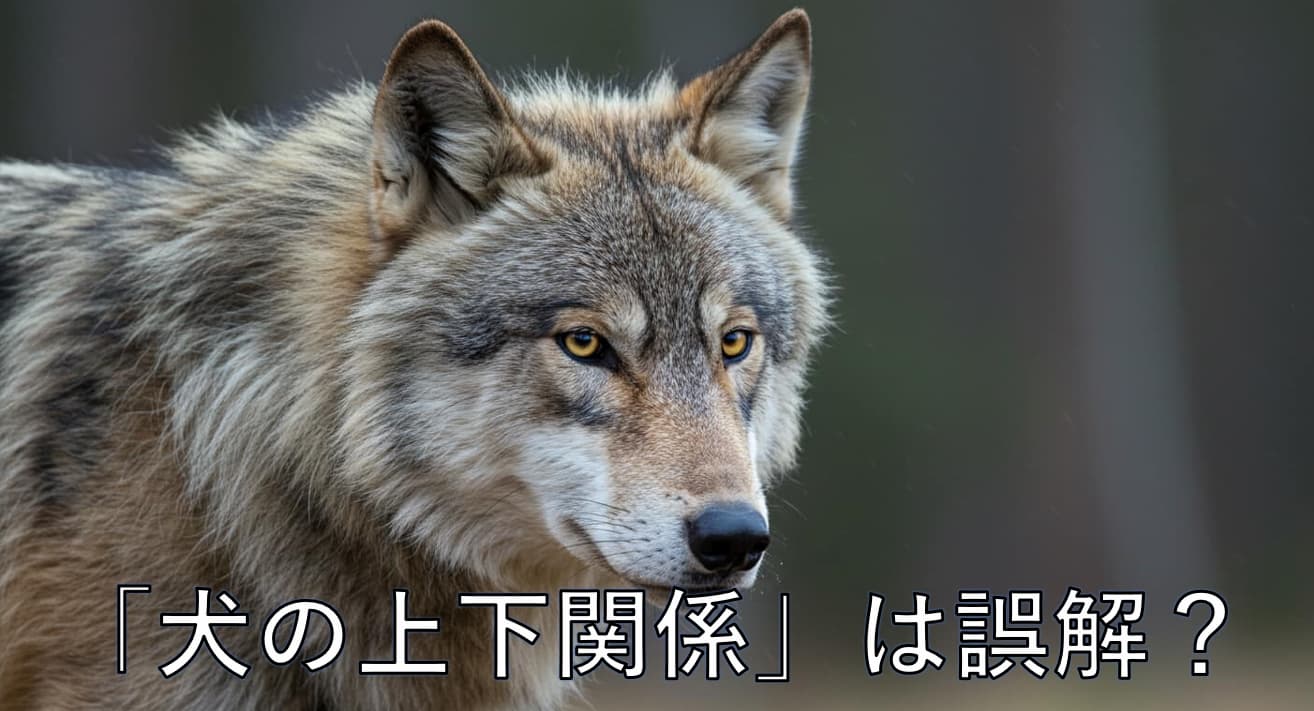長い間、犬は上下関係を重視し、強いものに従うと考えられてきました。犬の群には力で他者を制圧するボス(アルファ)が存在し、メンバーはこのボスに服従するという考え方です。この説は「支配性理論」や「アルファ理論」、「リーダー論」と呼ばれており、今でも支持する人は少なくありません。
皆さんも「犬にナメられてはいけない」、「犬が飼い主を下に見る」、「犬のしつけは上下関係が大切」といった主張を一度は聞いたことがあるでしょう。

しかし現在では犬を褒めるしつけが主流であり、リーダー論は学術的に否定されています。令和の時代でリーダー論を支持するドッグトレーナーは勉強不足だといわざるを得ません。
犬に上下関係を分からせる必要はありませんし、そもそも不可能なのです。なぜなら犬に上下関係という概念自体がないからです。
この記事では、なぜこのような誤解が生まれたのか、リーダー論の概要、およびもとになったとされるアルファ理論の提唱から衰退のまでの経緯を、詳しくお話しします。
※使用している画像は、全てAI生成によるイメージです。
リーダー論推奨トレーナーの主張内容と彼らへの反論についてはこちら
言葉の定義
一部のトレーナーが用いる、「上下関係を重視し力で従わせるしつけ」は、「支配性理論」「アルファ理論」「リーダー論」といった言葉で語られることがあります。この記事では、わかりやすさを重視し、一部のトレーナーが用いる考え方を「リーダー論」、もととなった軍用犬の育成方法を「支配的手法」、かつて動物行動学者が提唱した理論を「アルファ理論」と呼ぶことにします。
この3つの理論は混同されがちですが、実際には出どころも内容も異なる別のものです。それぞれの意味をきちんと区別しながら、解説を進めていきます。
リーダー論とアルファ理論の歴史と広まり
現在では学術的に否定されており、リーダー論が犬のしつけに使えないことは明白です。この理論は、学術的な観察と研究に基づいたアルファ理論と混同されることがあります。このアルファ理論は学術的な研究に基づいたものでしたが、それですら現在は否定されているのです。
学術的な主張であっても間違いはあります。大切なことは、間違いが判明したときにすぐに修正すること、そしてなぜ間違いが発生したかを知ることです。
「間違っている理論は学んでもしかたがない」と思わず、間違った理論が提唱されたきっかけや、広まった経緯を知っておきましょう。それは、現在推奨されているトレーニング理論の理解にもつながります。
軍用犬・警察犬訓練における支配的手法

支配的な訓練法の歴史は、1900年代初頭まで遡ります。ドイツのコンラート・モスト大佐が軍用犬や警察犬訓練にて服従の強制や罰をメインに用いていました。当時の軍用犬や警察犬訓練は、人が犬を支配し強引に従わせる手法が当然のように行われていたのです。
これは犬の福祉を度外視し、効率だけを重視した結果です。10頭訓練し、2~3頭が軍用犬として利用できれば充分。脱落した犬は処分しても構わないという考えに基づきます。当時、犬の福祉を訴える声は少なく、使役犬の育成にあてられる費用や時間も限られていたため、このような手法が取り入れられたのです。
つまり軍による支配的手法は、
- 効率だけを重視し、一部の犬だけ残せばよい。脱落者は早急に処分しても構わない
- 動物福祉を度外視する
という条件の下であれば、とても理にかなった手法であるといえます。面倒な分析や個性に合わせる作業を省きたい者にとって、これほど都合のよい手法はありません。この都合の良さこそ、昔のトレーナー(訓練士)が支配的手法を家庭犬のしつけに取り入れた理由です。しかし、家庭犬のしつけは上記の条件を満たしていません。
アルファ理論の発表と普及

トレーナーが主張するリーダー論は、動物学者が提唱したアルファ理論と同一視されがちですが(奥田順之 2018 et al.)、両者は全く別の物です。アルファ理論が「群の中に力が強く有利な個体と、弱く不利な個体があり、強い個体が群を統率している(Mech, D. L 1970)」としているのに対し、リーダー論では「強い者に従う本能がある(Millan, C 2015)」と主張しています。
学術研究に基づく「アルファ理論」はルドルフ・シェンクルがスイスのバーゼル動物園で飼育されているハイイロオオカミを観察し、1947年にその原型となる動物学的記述を行ったことが始まりです。
その後1970年に出版された『The Wolf』にて、著者であるデイヴィッド・ミーチがシェンクルの理論を解説。この書籍は非常に強い影響力があり、アルファ理論は一般に知られるようになりました。ただし、ミーチ自身はこの時点で独自の研究を行っておらず、あくまでもシェンクルらの理論を紹介したに過ぎません。また、ミーチがこの理論を犬のしつけに応用するよう主張したわけでもありません。
ドッグトレーニング業界への浸透
1980年代前半には、ドイツの動物学者エリック・ツィメンも「アルファ」という言葉を用いて犬やオオカミの行動を説明しました。しかしツィメンのアルファと、シェンクルのアルファは内容が異なっています。
ツィメンが示した「アルファ」とは、「特定の状況(例えば食べ物を奪い合うときや、繁殖競争など)において一時的に優位に立つ個体」であり、状況に応じて変化するものです。一方でシェンクルのアルファ(アルファ理論)は「力が強く、常に群で有利な存在」でした。
さらに、両者は「支配」や「序列」、「服従」といった言葉も用いていたため、人間社会の上下関係を連想させてしまいます。これらの言葉の使用が「オオカミが強いリーダーに従う」という、間違った解釈の大きな原因です。そして、あたかもツィメンが「アルファ理論」を提唱したかのように、大衆の間に広まってしまいました。
リーダー論と家庭犬のしつけ
軍用犬や警察犬の訓練で用いられていた支配的手法は、1960年頃にウィリアム・ケーラーという人物により家庭犬訓練に取り入れられます。ケーラーは元々軍用犬トレーナーであり、家庭犬の特性や環境を専門に学んだわけではありません。彼は非常に冷酷な性格で、「犬の穴掘りを止めさせるには、掘った穴を水で満たし溺死寸前まで犬の顔を水に突っ込むことで罰を与える」などと主張した人物でした。
そして1990年から2000年代初頭に、メディアやシーザー・ミランをはじめとする一部のトレーナーがリーダー論を主張。「犬は強い飼い主に従う、飼い主は犬にナメられてはいけない」という間違った解釈が、一般飼い主に広く知られることとなります。
リーダー論はミーチやツィメンの研究をもとにしたのではなく、軍や警察犬の訓練法と類似した支配的手法に基づくものでした。しかしその内容は誤解されたアルファ理論との共通項が多く、あたかもリーダー論が科学的根拠に基づくものであるかのように受け取られてしまったのです。
リーダー論はアルファ理論をベースに提唱された理論ではありません。元々存在した都合のよい手法を正当化するために、アルファ理論が利用されたといった方が適切です。難しい分析を省き、支配性で楽にトレーニングを進めたい彼らにしてみれば、 誂え向きの理論が転がり込んできたといった感じでしょう。アルファ理論が提唱される数十年前から威圧的なドッグトレーニングは存在したのです。
アルファ理論の衰退と批判
1999年11月に、アルファ理論を最初に普及させたデイヴィッド・ミーチが、理論を撤回する論文を発表。野生のオオカミを観察したところ、動物園のような閉鎖的環境のオオカミとは行動が異なり、彼らにはアルファ(君主的なボス)は存在しないと結論づけました。

アルファ理論はそれを普及させた張本人の論文によって否定されている理論なのです。この時点でリーダー論を正当化する要素はなくなったといえます。
さらに、APDTなどのドッグトレーニング団体によってアルファ理論やリーダー論が批判されるようになりました。2010年を過ぎたころには、LIMAといった動物福祉を重視するガイドラインが一般に知られるようになり現在に至ります。
なぜ「飼い主がボスになるべき」というリーダー論が広まったのか?
では、なぜ間違った理論が広まったのでしょうか?その理由は複数考えられますが、次の3つが主な原因でしょう。
力でねじ伏せれば犬たちが大人しくなるから
これが一番の原因と思われます。実際、犬たちは力で威圧すると大人しくなることが多いのです。しかしこれを「服従」であると見なすことは不適切といわざるを得ません(※)。なぜなら、実際には恐怖で萎縮しているのであって、けっして服従しているわけではないからです。
犬たちの恐怖反応は人に対してだけでなく、雷や工事現場のブルドーザーなど、非生物に対しても見られます。仮に犬たちの反応が服従なのであれば、彼らはブルドーザーに対しても服従していることになります。ブルドーザーを「リーダー」や「ボス」とみなす動物など存在するでしょうか?
そもそも、「大人しい=いい子」と定義することに疑問を感じます。たとえ大人しくても、犬たちが鬱状態だったら健全な関係とはいえません。犬を飼う以上、犬も飼い主も心身共に健康であることが必要です。萎縮した犬たちは心身共に健康といえるでしょうか?
萎縮した犬を「いい子になった」と解釈するのは、動物愛護の点で問題があります。このような誤解は、観察力の欠如と後述する確証バイアスが主な原因です。

人間は錯覚する生き物だから
人間は錯覚する生き物です。日本人であれば、血液型と性格の関係を一度は聞いたことがあるでしょう。実は血液型性格診断は完全な迷信であり、両者に関係がないことが学術的に示されています。しかし、なんとなく関係しているように思えることがありませんか?これは確証バイアスという人間の錯覚メカニズムによるものです。
人間は、自分の考えを肯定する要素に目を向け、否定する要素を見逃しやすいという特性があるのです。たとえば、A型の人は几帳面と思い込むと、A型で几帳面な人を見かけるたびにその確証を深めます。A型で大雑把な人がいても気にかけず、自分の考えに当てはまる事例ばかりが記憶に残っていくのです。
これと同じで、一度「力で威圧すれば犬はいうことを聞くものだ」と思い込むと、その仮説を裏付ける事例ばかりが記憶に残り、否定する事例は見逃しやすいのです。こうして、「犬は威圧するのが正しい」と言う確証が強められていきます。
「上下関係」は説明する側(トレーナー)にとって都合がよいから
仮に噛みつく犬がいたとしましょう。本来であれば、噛みつく原因はケースごとに異なります。先天的要素、体の疾患、日常のストレス、飼い主の不適切対応、恐怖心など様々です。それを一つずつ確認し、原因を突き止めるには多くの時間と労力を必要とします。
しかし、「飼い主がナメられているから」「上下関係が築けていないから」の一言で片づけ、暴力で犬を萎縮させて噛みつく気力を奪ってしまったらどうでしょうか?根気よく原因を突き止める面倒な作業を省けますし、噛みつかない大人しい子になったように見えます(実際は犬が萎縮して鬱状態になっているだけ)。これで料金が貰えるなら、ドッグトレーナーは楽です。
楽でトレーナーにとって都合がよいから、学術的に否定されているにもかかわらずリーダー論を推奨する人がいるのです。リーダー論は噛みつきも吠えも、破壊行動も散歩中の引っ張りも、全ての行動を順位付けに還元できます。細かい分析がいらないので、トレーナーも飼い主も分かった気になります。
犬の行動は本来とても複雑であり、同じ行動でも原因は全てのケースで異なります。全く同じものなどないといっても過言ではありません。それを「飼い主がナメられているから」、もしくは「リーダーになれていないから」で全て片づけられたら、どれほど楽でしょうか。
犬のしつけや問題行動対処に「簡単」なものなど存在しないのです。中身を読み解かず、学術論文を単なる権威として利用するだけの悪質トレーナーにだまされないように!
野生動物の姿とリーダーの真の役割
タイリクオオカミは害獣として駆除された過去があり、警戒心の強い個体だけが生き残ったため、なかなか人間の前に姿を見せることがありません。そのため、自然界のオオカミの生態は長い間謎に包まれていました。
ホワイトウルフとリカオンの観察

ところが、カナダのエルズミア島に生息するホワイトウルフ(ホッキョクオオカミ)は人間が近づいてもあまり警戒しません。海に囲まれたエルズミア島は人間が訪れることがほとんどなく、ホワイトウルフたちも駆除されることなく生き延びてきました。ホワイトウルフは自然界のオオカミの生態を知る大きな手がかりだったのです。
このホワイトウルフを13年にわたり観察したところ、とても興味深い行動が見られました。上下関係が厳しいとされていたオオカミが、獲物を仕留めた際、幼い子供たちに優先的に食糧を与えていたのです。
もし、オオカミの群に序列があるなら、必ず親オオカミが先に食べるはずです。しかし彼らは、幼い子供を優先します。おそらく、少しでも確実に子供たちを生き残らせるための行動でしょう。確かに服従に似た行動を見せることはありますが、する側とされる側の個体は決まっていません(Mech, D 1999)。
これは君主制的なリーダー論や、序列を重視するアルファ理論とは矛盾する行動であり、オオカミたちが求めるものが「力」ではなく、「協調性」であることを示すものでした。
このホワイトウルフの観察と研究は、アルファ理論を普及させたデイヴィッド・ミーチによって行われ、後に理論を撤回するきっかけとなっています。
また、アフリカに生息するイヌ科の動物リカオンにも群の中に序列は見られません。それどころか狩りに出かける際、一定数のメンバーが同意しないと狩りを行わないなど、まさに民主主義のような一面があるという説もあります。
自然界に生息する犬科の動物たちに序列というものありません。おとぎ話では悪役扱いになるオオカミですが、実はとても愛に満ちた動物なのです。だからこそ、犬はオオカミと別れて人間のパートナーになれたのでしょう。
野生の猿にはボスザルも上下関係も存在しない

皆さんも「ボスザル」と言う言葉を聞いたことがあるでしょう。一般に知られるボスザルのイメージは、群を力で支配する存在です。これはアルファ理論のアルファと非常に似ています。勘のよい方はもうお分かりですね。そうです。あれは動物園のサル山特有のものであり、自然界のサルにボスザルは存在しません。
サルたちは肉食ではないので、協力して狩りをすることがありません。そのため、オオカミほどの協力関係はなく、食べ物のアクセスに関して優位な個体が見られることはあります。
しかし、その個体が群の行動に関して決定権を持っているかというと、そうではありません。強さと群の統率は別なのです。このことから、サルたちにも「強い者に従う本能」はないことがうかがえます。
また、南アメリカに生息するフサオマキザルは知性が高く、ニホンザル以上に仲間同士の協力関係が密であることで知られています。自己中心的な個体は仲間から嫌われ、孤立してしまうことも確認されています。自己チューが嫌われるのは人間もサルも同じなのでしょう。
ただし、サルにもオオカミにも群を導く存在はいます。これは、力で威圧する支配的なものではなく、群の行動を促す「提案者」のような存在です(Mech, D. L 1999)。
人間の集団でも、仲間と遊びに行くとき、率先して計画を立ててお店の手配までしてくれる頼りがいのある人がいるでしょう。これこそが野生動物に見られるリーダーの姿です。けっして力で支配しているのではありません。群が移動するとき真っ先に行動する者、狩りに出かけようと周囲を誘う者など、行動力があり周囲のメンバーをその気にさせてしまうのが自然界におけるリーダーなのです。自発的な行動によって「群を導く存在」と、「メンバーの協力関係」が群の生き残りに重要であるといえます。

動物たちが必要としているのは、リーダー論で紹介されるパワハラ上司のようなリーダーではありません。気に入らないことがあると暴力を振るう人と、行動力と決断力で周囲を引っ張る頼りがいのある人、あなたならどちらについて行きますか?
上下関係による支配が成り立つ特殊な環境
ではなぜ学術的な観察をしたにもかかわらず、アルファ理論という誤った解釈が提唱されたのでしょうか?
その理由は特定の条件を満たす環境下ではアルファ理論が成り立ってしまうからです。最初にアルファ理論を提唱したルドルフ・シェンクルが観察したオオカミは、この条件を満たしていました。その条件とは
です。
オオカミの群において、力のある個体が優先権を得るとするアルファ理論は、人間が飼育しているオオカミの行動をもとに提唱された考え方です。人間に飼育されているオオカミは、エサや寝床など生活に必要な物が限られており、常に争いが発生しています。
飼育されてるオオカミに上下関係やアルファが見られる理由
動物園など閉鎖的な場所で飼育されているオオカミは、集団で協力しながら狩りをする必要がありません。与えられたものを食べるだけの彼らにとって、もはや協調性は意味をなさず、いかに目の前の食べ物を独占するかが全てです。このような環境では、お互いを思いやるより自己中心的な振る舞いが生存率を高めます。そしてなにより、力が強い者が有利です。

ただしこの場合、支配されている個体は、ボスに従いたくて自発的に従っているのではありません。力の差があるので、物理的に逆らえないだけです。両者の関係は、武装したテロリストと人質の関係に似ています。皆さんはワンちゃんとそのような関係を望みますか?犬にもオオカミにも、「強い者に従う本能」などないのです。
さらに、彼らは幼少期から寝食を共にした家族のような集団ではありませんでした。成獣になってから人為的に集められた、「赤の他人集団」だったのです。つまり望んだ共同生活ではなく、人間に強制された共同生活。いわば難民キャンプのようなものといえるでしょう(Mech, D. 1999)。彼らの生活環境や個体同士の関係性は、自然界のオオカミとは大きく異なっているため、オオカミ本来の特性を知る観察対象としては不適切でした。
アルファ理論は、「閉鎖的環境で生活し、生命維持に必要な物資を赤の他人同士で奪い合う特殊な環境」におかれたオオカミをもとに提唱された特異的な理論だったのです。
家庭犬の環境とアルファ理論
「犬はサークルで飼うのだから、人間が飼育していたオオカミに近いはずだろう」と思う方もいるでしょう。しかし、よく考えてください。アルファ理論のベースは「閉鎖的な場所で生活し、生命維持に必要な物資を奪い合うオオカミたち」です。
皆さんは、ワンちゃんと一緒にサークルの中で生活し、食べ物や寝床を奪い合っているでしょうか?そんなことはないと思います。物資を提供する立場の飼い主と、提供を受ける側の犬の間に、力の優劣による上下関係が発生することはあり得ないのです。ただし、仮に同じベッドで寝ているとしたら、寝床の奪い合いがおきる可能性があるので、寝床は分けてください。
また、多頭飼いをしている場合、ご飯を同じ場所であげたり、ワンちゃんたち専用の寝床がない場合は、ワンちゃん同士で力の優劣による争いがおきる場合があります。多頭飼いをする際は、奪い合いがおこらない環境をしっかり作っておくことをお勧めします。
これらは本能による生存戦略的な争いであり、「群のリーダー」や「飼い主の順位づけ」とは意味が違います。
食べ物や寝床などを奪い合う必要がなければ、争いに意味はありません。仮に「うちでは飼い主と犬の間に上下関係がある」と感じるのであれば、それは飼育環境が適切でない証拠です。なぜなら適切な環境で飼育していれば、飼い主が犬に対して上下関係を主張しなければならないシチュエーションにはなり得ないからです。
人間にも見られる支配的行動とリーダーの違い
先に述べた閉鎖空間における行動は、オオカミ特有のものではありません。実は人間も閉鎖的な環境におかれると、自己中心的な行動が目立つようになります。ミーチ氏は閉鎖空間のオオカミたちを難民キャンプに例えました。難民キャンプというと、紛争地帯などを連想される方もいるでしょう。しかし難民キャンプは、このような極端なものでなく、もっと身近に皆さんでも体験しうるものがあるのです。それは……
です。
日本では国民性のためか、海外で頻繁に発生する略奪は聞いたことがありません。しかし、その代わり「クレクレ問題」が発生しています。クレクレ問題とは、災害時の避難所において食糧や災害用品を備蓄している人が、それらを持っていない人から「分けてくれ」と要求され、半ば強制的に物資を奪われる問題のことです。拒めば「独り占めするのか」と非難されます。
また、支援物資が届いた際には皆が我先にと取りに行くことで秩序が乱れます。少しでも遠慮する人や、ためらう人は物資を手にできず、自己中心的な行動をとる者が有利です。

このような状況では、自己中心的に周囲の人間から物資を搾取する「支配者」と、搾取される「被支配者」に分かれます。この自己中心的な支配者こそがアルファです。決してリーダーなどではありません。これは、普段の人間社会における上下関係(親子、上司と部下、師弟など)とは似ても似つかない、極限に追い込まれた特殊な関係です。
特殊な環境におかれた人間を観察して、「人間には強い者に物資を提供する本能がある」と言われたのではたまりません。しかし、私たちはこれと同じことをオオカミや犬に対してやってしまっていたのです。
まとめ
この記事ではナチスなどによる警察犬・軍用犬の訓練法やリーダー論、アルファ理論について解説しました。それぞれの理論の概要をまとめると、次のようになります。
| アルファ理論 | 閉鎖的空間で人間に飼育されたオオカミの関係を観察した理論 |
| 軍の支配的手法 | 効率を重視し、動物福祉を度外視した訓練法 |
| 現代のリーダー論 | 軍の支配的手法をアルファ理論によって正当化した理論 |
かつて広く信じられていた「アルファ理論」は、動物園という特殊な環境下で観察されたオオカミの行動をもとに生まれたものでした。ですが、自然界に生きるオオカミたちは、力によって他者を支配するのではなく、親子としての絆や協力関係の中で生活しています。
アルファ理論の正体は、決して群れのリーダーなどではなく、追い詰められた生き物の生存本能による利己的行動だったのです。オオカミにも犬にも「強い者に従う本能」などありません。そこにあるのは「強い者には逆らえない」という悲しい物理法則だけでした。それは家族のような日常的関係とはほど遠い、武装したテロリストと頭に銃を突きつけられた人質の関係そのものです。
- 犬がいうことを聞かないのは飼い主を下に見ているからだ
- 犬に主従関係を分からせなければならない
- 犬にナメられてはいけない
- 犬が前を歩くと自分がボスであると勘違いする
- 犬は強い飼い主に従う
これらの主張は全て学術的な根拠がなく、細かい分析を省きたがる一部の職務怠慢トレーナーによって生み出されたナンセンス理論です。
現代の研究は、犬がオオカミと共通の祖先を持つ動物であり、支配されることで言うことを聞く動物ではないということを示しています。犬の問題行動を「ナメられているから」と片づけるのは、犬を正しく理解しようとする努力を放棄することと同じです。
犬のしつけに近道はありません。問題行動には必ず理由があり、それを丁寧に読み解き、対話し、寄り添っていく姿勢こそが大切なのです。犬を「支配」するのではなく、犬と「協調」するしつけを目指しましょう。
最後にもう一度、重要なことを記述して終わろうと思います。
参考文献
Mech, L. D. (1999). “Alpha Status, Dominance, and Division of Labor in Wolf Packs,” Canadian Journal of Zoology, 77(8), 1196–1203.
Mech, L. D. (1981). “The Wolf: The Ecology and Behavior of an Endangered Species,” Minneapolis, MN: University of Minnesota Press
奥田, 順之. (2022). 犬の問題行動の教科書. 緑書房.
奥田, 順之. (2018). 犬の咬みグセ解決塾. ワニブックス
Millan, Cesar. 藤井留美訳. (2015). ザ・カリスマ・ドッグトレーナー シーザー・ミランの犬と幸せに暮らす方法55. ナショナルジオグラフィック
菊池, 聡編. (2014). 錯覚の科学. NHK出版.
ナショナルジオグラフィック, (2021). キングダム・オブ・ホワイトウルフ. Desney+
Miller, Pat. (2019). Debunking the “Alpha Dog” theory. Animal Health Foundation. https://www.animalhealthfoundation.org/blog/2019/11/debunking-the-alpha-dog-theory/, (2025/07/23閲覧)
Wason, Traci. 鈴木和博訳. (2017)リカオンがくしゃみで投票、合意形成か. ナショナルジオグラフィック http://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/090800342/, (2025/07/23閲覧)
矢方, 滉将. (2025). 「【避難所の闇】衝撃の備蓄品没収とクレクレ被害に遭う防災グッズ5選」. マイベストプロ大分 https://mbp-japan.com/oita/yawoki/column/5196828/, (2025/07/24閲覧)